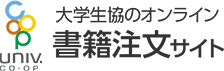病気であって病気じゃない

1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります
精神科は実体のない病気を扱う診療科である。それゆえに、「病気である」「病気ではない」という判断をする場面で精神科医と患者はときにすれ違う。
本書では、精神科診療における「病気」の概念を、さまざまな階層で述べていくことで、精神科医と患者の間で起きているすれ違いを臨床的に解きほぐしていく。
そしてその先に、この「病気か否か」という二元論を克服することを提案したい。
つまり、私たちが診ている人はいったんすべて「病気であると同時に、病気ではない」という概念を持ち込んでみる、という提案である。学術と創作の境界が溶けゆく長い思考の旅へようこそ。
【目次】
第1部 病気には実体がない
1 「病気」という言葉から連想されるもの
2 病気であると扱うこと・扱われること
3 病気じゃないと扱うこと・扱われること
第2部 病気であって病気じゃない─理論編
1 精神科医が「病気であって病気じゃない」と考える効能
2 内科において「病気であって病気じゃない」と考えることの意味
3 一般の人が「病気であって病気じゃない」と考えることの意味
4 病気や病名を巡るコミュニケーションが象徴的になること
第3部 病気であって病気じゃない─実践編
1 ADHDの新卒男性は、病気であって病気じゃない
2 HSPを自称する地雷系女子は、病気であって病気じゃない
3 誹謗中傷キッズは、病気であって病気じゃない
4 典型的な双極症Ⅰ型は、病気であって病気じゃない
5 トーキョー後遺症は、病気であって病気じゃない
6 教え子に振り回される大学院生は、病気であって病気じゃない
7 認知症の家族は、病気であって病気じゃない
8 あなたが「病気であって病気じゃない」かどうかは知らない
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。