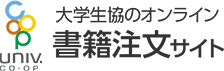百年の偽善

1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります
緻密に作られた作品だからこそ、緻密に読めば読み解ける。
夏目漱石(1867-1916年)の後期三部作のひとつとして名高い『こころ』(1914年刊。あとの二作は『彼岸過迄』『行人』)は、まさにそうした作品であることを解き明かしていく一冊。
通常、『こころ』は、「人間の葛藤とエゴイズム」を描いた名作、あるいは明治天皇の崩御と乃木大将の「殉死」と呼応する作品として文学史に登場するが、著者はその双方に疑問を突きつける。
著者は、漱石自らが著した『文学論』に立脚しつつ、作中で使われた言葉の表現や会話のやりとりに注目する。すると、〈実際に場面として展開していること〉と、それが〈作品全体としてなんのために行われているのか〉に意図的なズレがあることがわかってくる。そしてそれを手がかりに「作品の真」へと迫っていく。
「葛藤している人物/エゴイズムに苦しむ人物」ように見える「先生」は、ほんとうにそのような人物なのか。ある意味「残酷」な読み解きによって、「先生」が何を隠していたのか、先生の死(「殉死」とされる死)とはなんだったのか、これまでにない解釈を提示する。
文学史上不朽の名作とされる『こころ』が、一般の読者にとってもなぜ名作たりえるのか、漱石の小説創作の巧みさとともに明白にしていくスリリングな一冊でもある。
お気に入りカテゴリ
よく利用するジャンルを設定できます。
カテゴリ
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。