理科教室 No.812(Vol.65 No.8)
特集:防災地学教育はしるところから
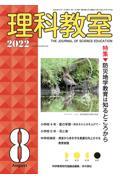
出版社よりお取り寄せ(通常3日~20日で出荷)
※20日以内での商品確保が難しい場合、キャンセルさせて頂きます
防災・減災につながる地学教育とは、気象・流水のはたらき・地形と地質・地震・火山などを科学的に理解し、現れる諸現象を予想し、備え、いざというときの行動ができるようにすることでしょう。
大雨が降れば流水のはたらきが大きくなります。そしてそれは河川経路と地形や地質の影響を受けます。洪水だけでなく土石流が発生する場合もあります。子どもは地域でどのような気象災害が想定されるか理解できるでしょうか。
日本沿岸部ではどこでも、海底が震源の場合は地震動の被害に加えて津波の被害が想定されます。子どもはそれが分かり、命を守る行動に結びつくでしょうか。
個性的な噴火でも予測できる場合があります。マグマが動くときに発生する火山性地震を追えばマグマの移動がわかります。2000年3月、北海道の有珠火山観測所はそのようにして噴火を予測し、洞爺湖町の全町民と観光客を避難させ、一人の犠牲者も出しませんでした。
このように活火山の観測網の整備と観測データを解析する研究者チームの体制づくりを進めれば、予測の可能性が高まります。住む地域に影響する火山ではどうでしょうか。
地域の各種災害を想定し、危険度を示すのがハザードマップです。ハザードマップを活用しながら地域教師が連携して防災のための地学教育を進めることで、減災につなげる行動ができる子どもを育てようではありませんか。
(「主張 防災地学教育は知るところから 科学的知識を身につけ 減災に通じる行動を」鈴木 邦夫(編集部)より抜粋)
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。



