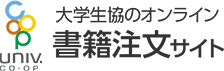青空と文字のあいだで

1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります
戦禍と災厄の暗がりを縫って「かけがえのない離脱のとき」を生きるために。
文明の黄昏のなかで紡がれた犀利な思考の記録。【帯文:栗原康氏】
文明とは、法を策定しつつ、われわれを巨大建築(ピラミッド、城、教会、タワマン、原発…)の建造へと動員する奇妙な意思である。だが、今世紀には世界貿易センタービルが倒壊し、原発が爆発し、高層住宅が叢生する中国からパンデミックが発生し、ついにはまたも文明の原郷のひとつで戦争がはじまってしまった。破綻の徴候はあきらかである。おなじことは法についてもいえる。そもそもこの数十年にすすめられてきた「規制緩和」とは、法そのものの溶解にほかならない。
本書はこの10年あまりに書きつがれた文章の集成である。文明の黄昏のなかでの思考の痕跡といってもいい。第I部で語られるのは、離脱が蜂起となる理路である。現代思想の開始をつげたレヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』は、社会からの離脱と労働の中断を言挙げしておわる。その思考はやがて「ジレ・ジョーヌ(黄色いベスト)」たちの蜂起へと結晶するだろう。第Ⅱ部では、そうした蜂起の諸契機が「就活」や「婚活」といったわれわれの日常のなかにさぐられる。
そして第Ⅲ部では、概念としての「大学」がねりあげられる。大学とは施設でも制度でもなく出来事であり、文明やそこから派生する国家からの離脱である。だからつねに蜂起とともにある。本書になにがしかの今日的な意義があるとすれば、離脱が蜂起でもあるような境位としての大学にふれていることだろう。文明はおわるのだろうか? われわれは法の裁きと決別できるのか? たしかなことは、文明のもとで戦争は不可避だということである。そして文明後のユートピアとは、おそらく大学のいとなみだけが無償の義務であるようなアレンジメントである。文明が潰えても、青空と文字のあいだで、われわれは語りつづけ、歌いつづけるだろう。災厄と戦禍の暗がりのなかで、本書がなつかしくもあたらしい歌を口ずさむささやかな手がかりとなればと願う。(しらいし・よしはる)
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。