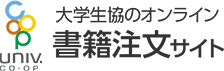ドレスコード

1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります
17世紀、ルイ14世は自分と廷臣以外の赤いソールの靴着用を禁止し、21世紀、クリスチャン・ルブタンは赤いソールの商標を独占した。彼らは赤い靴底ではなく「権力と特別感」を守ろうとしていた。なぜなら「服装」にはそれだけの効き目があると知っていたからだ。
宮廷と修道院、革命と公民権運動、娼婦と淑女、ギャングとセレブ。「階級・性差・貧富」を表し、固定するものとしてドレスコードは機能していた。そしてフランス革命後の「国家と個人の誕生」とともに、服装は自由と平等を実現し、一人ひとりの個性を表し、格差を破壊するものになる――はずだった。
それにもかかわらず、アメリカの高校は現在も服装規定を増やし、レストランは髪型を理由に従業員を解雇する。「流行なんてどうでもいい」とTシャツを好むIT起業家たちは、「ファッションに無関心という最新の流行」に夢中になっている。ドレスコードに隠されたメッセージは形を変え、今なお生きているのだ。
ジャンヌ・ダルクは異性装でパワーを手にするもタブーに倒され、おしゃれをした黒人は「身のほど知らず」だとリンチにあい、現代の女性はメイクをしてもしなくても批判される。イタリア人の無造作なネクタイは絶賛され、スコッチテープでネクタイを固定したトランプは馬鹿にされる。服装は女性の趣味ではない。人類がパワーゲームのために用いてきた暗号であり、今でも社会と個人に密接に関わる重要な要素だ。
私たちがドレスコードに縛られるのはなぜだろう? 服装が取り決め、ルールや法、裁判所命令の対象になるほど絶対的になるのはどんなときか? ドレスコードが、平等や個人の自由に関する社会規範の変化と衝突したら何が起きるのか? ドレスコードが役立つのはどんなときで、必要以上に抑圧的になったり、不当なものになったりするのはどんなときか?
歴史をひもとけば人は服につくられてきた。それなら服装は本当に個人が選択しているのか? 時代の流れに知らぬ間に同調し、周囲に好印象を与える――あるいは人の気を引くためにその服を着ているのだろうか?
本書は、歴史を通したファッションの法則を探り、服装――自己表現の最も私的かつ公的な媒体――が持つ個人的、社会的、政治的な意味を明らかにしていく。階級、性差を表す「暗号」だった歴史的なドレスコードを読み解くとともに、人種、ジェンダーの平等をめぐる戦いの中で、服装がどのような役割を果たしてきたのかを考察する。そしてこのテレワークの時代、消えない分断の世界で、「これからのドレスコード」を問う。
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。