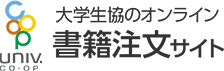天国と地獄、あるいは至福と奈落
ルネサンスの北方世界においては、人びとの興味はいずれ赦されて到達する天国ではなく、避けることのできない煉獄へと向けられた。かつて宝石で囲われた城塞都市として表現された天上のエルサレムは、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンやハンス・メムリンクが描いたように、入口だけが示されるにとどまり、観者が目にすることになるのは、キリストを囲む聖なる人物の集団によって暗示される天上世界か、祝福された人びとが天上へ向かうまでの穏やかな地となった。対する地獄についても同様の傾向が見られる。ヤン・ファン・エイクは擬人化された死を表現し、悪魔たちに責めさいなまれる魂を描いたが、ロヒールは魔物を描かず、悪しき魂たちを自主的に懲罰の地へと向かわせた(本書第1章)。病院という死にゆく人びとのための場所に設置された祭壇画は、正義の図として裁判所に掲げられた審判図とは異なる役割を果たしていたのであろう。キリストの口からは『マタイによる福音書』の呪詛の言葉(第二五章四一節)が発せられようとも、人びとが落ちていく炎の先は浄罪の地であり、《ボーヌ祭壇画》の依頼主であるニコラ・ロランが故郷のオータンで見あげていた地獄とは異なる(本書第2章)。
当時流行した幻視文学は、そうした審判の時までの贖罪という考えを反映していると言えよう。テキストによって具体化した贖いの場所は、写本挿画と相まってタブローにも変化を与えた。恐ろしい怪物や残酷な責め苦も、いずれ救済されるのであれば、地獄への眼差しは「怖いもの見たさ」に変わる。入口のみ示されていた地獄はボスによって再び懲罰風景が表現されるようになるが、そこはあくまでも浄罪の地であり、未来永劫続く苦しみを背負った悪しき魂が表現されているわけではない。シモン・マルミオンによるトゥヌグダルスが体験した彼岸の世界の図像化は、ボスによって展開される悪魔によって罰せられる魂の表現に貢献したことは明らかである(本書第3章、第4章)。
このような図像の変遷は、天上世界の表現にも変化をもたらすことになった。天上のエルサレムは具現化されず、失われた楽園がとってかわる。かつてボスが描いたエデンは、楽園というより原罪という人類最初のカップルが犯した罪に重きを置き、対置される地獄とともに罪の贖いという側面が強調されたが、時代を経るにつれその意味は変わっていく。
こうしたエデンの楽園図像の変遷は、ルネサンスと時を同じくする大航海時代とのかかわりが指摘できる。各地からもたらされる珍しい動植物は、創造主としての神の力をあらためて人びとに感じさせたことであろう。ペーテル・パウル・ルーベンスとヤン・ブリューゲル(父)の作品に見られるように、エデンの楽園を描くことは、単なる罪の表象にとどまることなく、神がつくりたもうた世界の多様性に目を向けるとともに、追放された理想郷への回帰となった(本書第5章)。
死という避けられぬ運命に向きあうため、人はさまざまな対処法を生みだしている。当時宗教の果たす役割は大きく、死後の世界での幸
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。