KOKKO 第43号(5 2021)
特集1:労働組合の「メリット」/特集2:デジタル改革は誰のため?
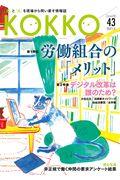
出版社よりお取り寄せ(通常3日~20日で出荷)
※20日以内での商品確保が難しい場合、キャンセルさせて頂きます
[第一特集] 労働組合の「メリット」
労働組合の価値を伝える言葉とは
本特集は、労働組合の「メリット」という言葉をめぐる葛藤を通じて、労働組合の価値とそのあり方について議論すべく企画しました。
今号で映画評連載が最終回となった熊沢誠さんの『労働組合運動とはなにか』(岩波書店、2013年)によれば、労働組合の基本的な機能は、①労働力商品のダンピングを防ぎ価格の標準化を行わせる機能(経済的機能)、②労働者の生活を左右する労働条件への当事者の発言権・決定参加権を保障する「産業民主主義」を担う機能(政治的機能)、③生活上の具体的な必要性と可能性を共有する「可視的ななかま」を意識的な居場所や帰属集団にする機能(社会的機能)、などに大別されます。こうした労働組合運動は「ノンエリートの自立」、つまり苛烈な個人競争を勝ち抜かずとも支配されたり操作されたりせず自立して働き暮らせる社会をつくるために、最も重要な拠り所となります。
労働組合の組織率が低下し、必ずしも人びとがそうした前提を共有しなくなったとき、どう対話すれば労働組合の価値や必要性を伝えられるか。「メリット」という言葉から、古くて新しい労働組合の存在意義を考えます。
[第二特集] デジタル改革は誰のため?
公務員を「国民全体の監視者」「一部のIT企業の奉仕者」に
コロナ禍の日本において、特別定額給付金の支給に時間を要したことや教育現場でのオンライン対応に不備があることなど、行政・社会のデジタル化の遅れが露見しました。それならば、国民の暮らしを守るためにデジタル化をすすめる必要があると考えるのが普通ですが、菅義偉首相は、「デジタル化の流れに乗り遅れ、新たな成長の原動力となる産業が見当たらない」ので「次の成長の原動力をつくり出します。それが、『グリーン』と『デジタル』です」(第204回国会施政方針演説)と明言しました。今後も続くであろうコロナ禍において、国民の暮らしを守るために行政のデジタル化をすすめるのではなく、産業における新たな成長戦略として、企業に最大限の利益をもたらすためにデジタル化をすすめています。法律家からは菅政権のすすめるデジタル化は「デジタル監視社会化」だとの指摘もされています。
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(憲法15条)のに、公務員を「国民全体の監視者」「一部のIT企業の奉仕者」に変質させてしまう危険性もあります。第二特集ではデジタル改革がいったい誰のためにすすめられているのかを考えます。
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。



