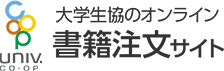英国レコーディング・スタジオのすべて

取り寄せ不可
- 出版社
- DU BOOKS
- 著者名
- ハワード・マッセイ , 新井崇嗣 , 井上剛 , KENJI NAKAI
- 価格
- 4,400円(本体4,000円+税)
- 発行年月
- 2017年11月
- 判型
- A4
- ISBN
- 9784866470313
- ※現在ご購入いただけません
- お気に入りリストへ追加
黄金期ブリティッシュ・サウンドが生まれた「現場」を知る!
1960〓70年代のロック名盤を生んだ、45の録音スタジオと7つのモービル・スタジオの詳細なデータを収録。
コンソール、マイク、テープマシン、アウトボード、ルームの様子、スタジオ固有の音響テクニックなどがわかる!
エンジニアやスタッフが回想する名盤誕生にまつわる逸話(数多のドタバタ、ひらめき、冷や汗)も掲載。
ハワード・マッセイは『ビートルズ・サウンド 最後の真実』の共著者。
日本語版は、国内外で活躍するレコーディング・エンジニアの井上剛氏とKenji Nakai氏が監修。
「レコーディングについて書かれた本のなかで間違いなく最重要の一冊……
爆発的発展期の英スタジオシーンに関する情報の宝庫だ」マルコム・アトキン(APRSチェアマン)
本書“イントロダクション”より
ポップミュージックの“黄金期”――ロックンロールがけたたましくシーンに登場した50年代半ば頃から、70年代後半、ドラムマシンといったデジタルオーディオ機器が音楽の非人間化に向けて、情け容赦のない行進を始めるまでの間――には、これは大英帝国で作られたレコードだと教えてくれる、米国で作られたものとは一線を画する“英国の音(ブリティッシュ・サウンド)”が紛れもなく存在した(中略)。
音の相違は如実な場合もあれば、微妙な場合もあるけれど、大英帝国のスタジオ(大半はロンドンにあった)で生まれたレコードと、ニューヨークのA&RやナッシュヴィルのRCAスタジオB、ハリウッドのキャピトル・タワーで作られたものとの間には、間違いなく客観的な違いが存在する(後略)。
先導役はザ・ビートルズであり、彼らはジョージ・マーティンやEMIエンジニア陣による協力の下、聴衆の受容力の限界を試し、押し広げるレコードを絶えず創造し、既成概念の枠を止むことなく超えていった。
彼らのあとに他の英アーティストたちも続き、新たな要素を次々に自らの音楽に組み入れ、手持ちの道具の限界を試し、押し広げていった。そして60年代半ば、英国の録音は革新性に関していえば、米国で、いや世界中のどこでなされたどれと比べても遜色のない、あるいはどれよりも優れたものになっていた。
端的に言えば、“英国の音(ブリティッシュ・サウンド)”は、いるべき人がいるべきときにいるべき所にたまたまおり、彼らの創造的構想を実現するのに必要な道具が手元にたまたまあり(あるいはなく)、相反する技術的“標準”の数々が途方に暮れるほど膨大に存在するのが当たり前という激動期をどうにか乗り切れるだけの力が彼らにたまたまあった、という偶然の積み重なりから生まれた――そしてそこにはさらに、偶然の幸運と不運もたっぷりとあった。
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。