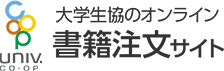支那論

1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります
中国をどう見るか、中国にどう向き合うか――これこそ日本にとって、最も重要で、最も難しい課題である。そして今日、中国の急速な台頭を前にして、われわれにとって、いっそう切実な課題となっているが、最も頼りになるのは、内藤湖南の中国論であろう。なかでも戦前、最も読まれ、同時代中国を論じた『支那論』(1914年)と『新支那論』(1924年)を本書は収める。
湖南は、『日本人』『万朝報』『大阪朝日新聞』『台湾日報』などで、ジャーナリストとして活躍した後、京都大学に招かれ、東洋史学講座を担当した。中国史全体に関する学者としての博識と、中国現地でのジャーナリスト経験を合わせもつ稀有な存在として、清朝滅亡以降、激動する同時代中国を観察し続けたのである。
その中国論は、一言で言えば、皇帝の権力が強くなる一方、貴族階級が消滅して平民が台頭し、商業が盛んになった北宋(960年~)の時点ですでに、中国は近世(近代)を経験した、というものである。
「支那の歴史を見れば、ある時代からこのかたは、他の世界の国民の……これから経過せんとしているところの状態を暗示するもので、日本とか欧米諸国などのごとき、その民族生活において、支那よりみずから進歩しているなどと考えるのは、大いなる間違の沙汰である」――湖南は、中国の民主化の挫折を予言するのであるが、それも、中国が「近世」の段階にすでにこれを経験・失望し、西洋や日本の「近代」での経験に先んじていたからなのである。
政治的独裁と経済発展が混在する現代の中国。湖南の中国認識は、今日、いっそうのリアリティを持っており、われわれ自身の中国認識の出発点となりうるだろう。
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。