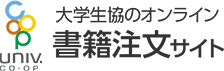脱「国際協力」
NGOは政府とのパートナーシップを追求するあまりに独立性を失ってはいまいか、そして社会変革への志向も薄らぎつつあるのではないか。本書の編者らが『国家・社会変革・NGO―政治への視線/NGO運動はどこへ向かうべきか』(新評論、2006年)を出版したのはそんな危機意識からであった。
国際協力の分野においてその危機は今、さらに深まりつつある。国益実現のツールとしての政府開発援助(ODA)の戦略的活用路線がますます明確になり、対テロ戦争と並行共存する平和構築が日本の国際協力政策の中核の一つに位置付けられるようになっているからだ。本書はこの危機の深まりを捉えるために、国際協力政策の背景やその依拠する考え方、そして国際協力という言説そのものの見直しに主眼をおいている。
本書の第一の特色は、非国家の視点から国際協力を論じている点にある。例えばODAを“援助する側”の論理ではなく“援助を受ける側”の視点で見れば、「開発援助」の思想と実態の“貧しさ”が見えてくる。本書のもう一つの特色は、問題提起と批判的省察の姿勢をもって主流の国際協力のあり方を検討している点にある。「平和構築」と呼ばれる一連の活動も、アフガニスタンなどの現場で起きていることを直視すれば、それが本当に平和を創出しているのか疑問に思わない方が難しい。むしろ“人道的帝国主義”と呼べるような事態が進行しつつあるといえる。
福島第一原発事故によって原発推進における産官学政一体の癒着構造が明らかになった今、主流から外れることを恐れず、国家におもねることなく、被害に遭い切り捨てられる人々の立場に立って物を考え行動し続けることの重要性を、今ほど痛感することはない。NGOの出発点もそこにおくべきではないか。(ふじおか・みえこ)
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。