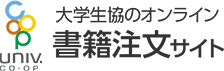妖精のささやき

出版社よりお取り寄せ(通常3日~20日で出荷)
※20日以内での商品確保が難しい場合、キャンセルさせて頂きます
「この書物は真の希望のメッセージである」--原書に付された紹介文にこう記されているとおり、本書は、どんな逆境にあっても人生をけっしてあきらめないための提案として書かれている。著者シリュルニクは、まず「序論」で、二十紀アメリカの女優マリリン・モンローと十九世紀デンマークの作家アンデルセンという、時代も場所も仕事もおよそかけはなれた二人を呼び出す。じつは、彼らには子ども時代にひどい虐待を受けたという、共通の過去があったのだ。そして、三十六歳で自殺したマリリンと、七十歳まで生きて多くの栄光につつまれ、今も世界中でその作品が読まれているアンデルセンとのちがいを、「打たれ強さ(レジリヤンス)」に求めて、女優がついに果たせなかった「打たれ強さ」の獲得に、作家が周辺世界と文化的環境の助けを得て成功する過程が強調される。
その後、第一部「ちびっこたち、あるいは絆づくりの年齢」では、親や周囲から虐待を受けた幼少年期の子どもたちが、彼らをとりまく人びととの絆をつくりあげることをつうじて、みごとに立ち直り、再び立ち上がっていく実例が感動的に描き出される。第二部「青い果実、またはセックスの年齢」では、思春期の子どもたちの、もう少し複雑な虐待からの復帰体験が、やはり豊富な実例とともに語られる。そして、「結論」で、著者は、誰もが「打たれ強さ」の熾火を奥底に秘めているのだが、熾火に息を吹きかけてやらないと火は消えてしまうことを指摘したうえで、現代人の大多数が体験している「トラウマ(心の傷)」を縫い合わせることで、熾火を燃え立たせて「打たれ強さ」を形成できれば、「想像もつかない太陽のような幸せ」が待っていると、私たちに呼びかけるのである。
本書の各章は「驚きがなければ現実からは何も生まれない」とか「家族と文化がその力をあたえるとき、学校は打たれ強さの要因となる」といった、具体的な提案に満ちた表題で、それぞれが三、四ページ程度のコンパクトな構成になっているので、読者は思わず先へ先へと読み進むことになるだろう。そこにあげられた数々の実例は、日本社会での子どもの虐待とは必ずしもぴったりと重なるものではないが、かえって新鮮な視点から、私たちの現実を見なおす手がかりを提供してくれる。
この書物の最大の特色は、シリュルニク自身が第二次大戦中に両親をナチの強制収容所で失った孤児であるということだろう。その後、さまざまな困難を乗り越えて(と言い切ってしまうには、あまりにも過酷な出来事も当然あっただろうが)パリ大学医学部で学び、精神医学から比較行動学までの広範な研究をつうじて、現代フランスを代表する知識人となった著者の人生そのものが「打たれ強さ」のみごとな例証となっているのである。
(本書「訳者後記」より)
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。