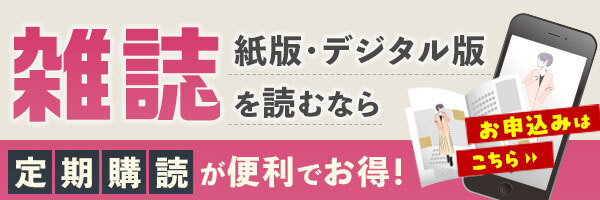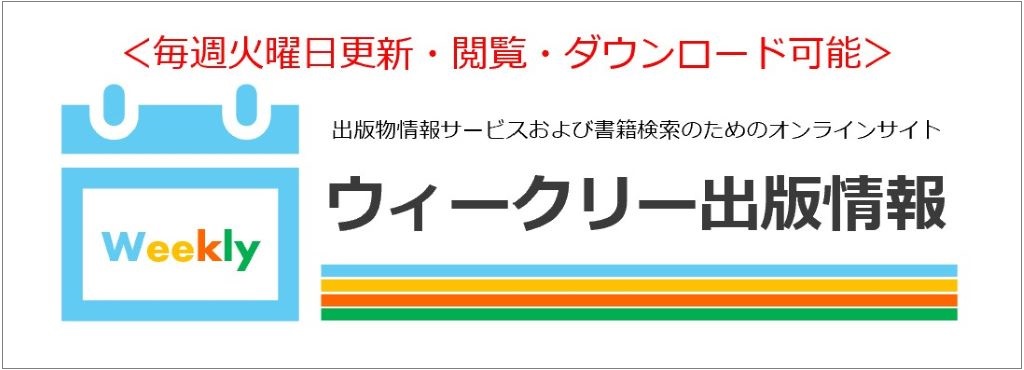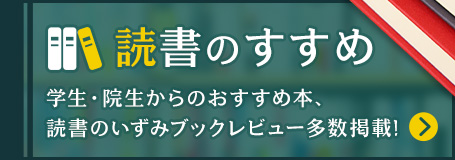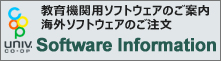溶接構造物の疲労の基礎

出版社よりお取り寄せ(通常3日~20日で出荷)
※20日以内での商品確保が難しい場合、キャンセルさせて頂きます
- 出版社
- コロナ社
- 著者名
- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 , 山田健太郎
- 価格
- 3,960円(本体3,600円+税)
- 発行年月
- 2023年10月
- 判型
- B5
- ISBN
- 9784339052800
繰返し荷重を受ける鋼構造物では,しばしば疲労が問題となります。本書では,特に鋼道路橋の溶接継手を対象として,その基本的な疲労挙動を解説します。本書の内容は,鋼道路橋以外の溶接構造物に適用することも可能です。
本書は,つぎの3部で構成され,疲労の基礎を理解して,疲労照査に応用する観点からまとめられています。
第Ⅰ部 溶接された鋼構造物の疲労強度 ─基礎的な考え方─
疲労の勉強を始める方は,まず第Ⅰ部で全体像を把握して欲しい。ここでは,溶接鋼構造物の疲労耐久性の評価に関する全体の流れを説明します。そこでは,繰返し荷重が作用する鋼構造物の疲労では,疲労の3要素,すなわち①溶接継手の形状,②作用する応力範囲,および③その繰返し数が重要であることを示します。
第Ⅱ部 各種の溶接継手の疲労挙動 ─基礎から応用へ─
疲労強度は,溶接継手の形状によって異なるS-N曲線で表現されます。そこで,各種の溶接継手の疲労試験結果から,それらの疲労挙動を比較して,疲労耐久性に影響するパラメータについて解説します。鋼橋などの大型の鋼構造物では,疲労試験機の容量の制約から実物での疲労試験は難しいので,その一部を取り出した溶接継手で疲労試験されます。ここでは,比較的板厚の小さい鋼板(10~20mm程度)の溶接継手の疲労試験を参考にしています。
第Ⅲ部 道路橋の使われ方と損傷事例 ─作用する繰返しの外力と疲労き裂─
ここでは,筆者が関わった道路橋やその付属物を対象として,疲労損傷事例とその対応について概説します。既設の道路橋は,設計や製作,架設,供用中の維持管理など,それぞれが異なる経歴を持ちます。そのため,疲労の知識だけではなく,設計から維持管理に至る一連の流れも念頭に,耐久性や補修・補強について考える必要があります。
また,疲労損傷を生じた実際の鋼道路橋について,その原因の調査や耐久性の評価,補修・補強の基本的な考え方を示します。これらは,筆者が関わった事例の一部であり,関与した橋梁技術者や道路管理者との議論の成果です。ただし,本書で引用する内容には,筆者の私見も含まれています。
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。